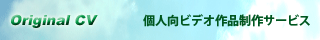▲Top
作品名「積日 それから」
撮影・編集 Original CV 制作 福岡県女性
作品時間 39分
- 6年前の春、父が亡くなった。その夏、私は志を固めて、当時勤めていた会社を辞めた。そして、その秋、父の遺骨の一部を大谷本廟に納めるため、母と兄夫婦と私の4人で京都へ向かった。母と私はその足で、母の実家の新潟へと旅を続けた。
ビデオ作品「積日」はその旅の記録をまとめたものである。父亡き後、私たち家族がどのように生きていくのか。そのスタートとなった作品でもある。
そして、それから6年の歳月が経った。
母は85歳にして両膝の手術を受けて歩けるようになり、白内障の手術も受けて、よく見えるようになったという。その母がこの機会に再び、新潟の実家へ旅をしたいと言い出した。
11月23日、母と兄夫婦は羽田空港へ到着した。私の準備した車に乗り込み、新潟へ向けて関越道に入った。関東平野は雲ひとつない快晴。雪化粧した浅間山の裾野が長く見えている。赤城山の紅葉も一段と美しい。
谷川岳には雲が重くかかっている。そして、そのトンネルを抜けると、別世界だった。川端康成の小説「雪国」の通りだ。
母は十代の頃、「自立したい」という夢を叶えるために、新潟と東京を何度も往復した。母にとっては懐かしい光景なのか、いつになく無邪気に、はしゃいでいるように見えた。
新潟の母の実家へ到着すると、すぐに荷物を置いて、近くの病院へ向かった。
病室に入ると、目的の人はベッドに横になっていた。私たちの突然の訪問に驚いた様子だったが、体を起こして少しずつ会話を始めた。
「舞鶴港のこと、覚えていますか。みんな忙しくて来れないと言うので、あなたが親戚を代表して、私たちを出迎えてくれたのよね。ありがとう。もう日本に戻ることはないと思っていたのに・・・。
あのとき、あなたはきちっと学生服を着ていましたね。」
「高校3年生でした。」
昭和28年、父と母と当時2歳だった兄は満州から帰国した。終戦後8年も経っていた。当時の高校3年生は舞鶴港で父と母を出迎え、2歳の兄を抱きかかえたという。
母は兄を指し、「あなたとこの子は従兄弟同士になるのかしら。」
母は続けて、「似ているわねえ。」と話すと、ベッドの上の人は目を閉じて天を仰いだ。そして、左手でタオルを鷲づかみにし、目を覆った。不自由な体で出来る数少ない動作だった。
長く積み重ねた日々。決して忘れることはないすべてが一度に昇華してしまう瞬間だった。
母は今回の旅で最も会いたい人に出会えたのだった。
- メールマガジン No. 64 2008-12-01